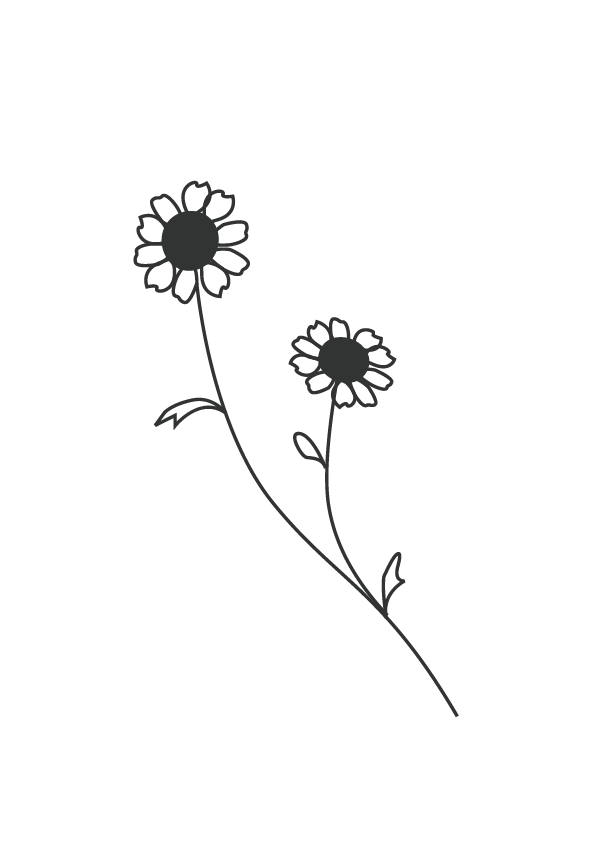導線・構成・伝わるデザイン力が身につく!
「デザインって、結局センスでしょ?」
…そう思っていたのは、かつての私です。
だけど実際には、“伝わるデザイン”はセンスじゃなくて「構造」や「考え方」で身につくことが、ある本を読んでから分かったんです。
「バナーを作っても、なんかダサい」
「プレゼン資料、詰め込んだのに読みにくいって言われた…」
「SNS投稿、頑張ってるのにスルーされる」
そんな経験、ありませんか?
安心してください。デザイン初心者が最初につまずくポイントは、みんな一緒。
私もずっと「色合わせが下手だから」「おしゃれなフォントが分からない」と思い込んでました。
でも実は、“見る人が迷わない配置”や“ちょっとした余白の取り方”を知るだけで、印象はガラッと変わります。
今回ご紹介するのは、「これ、もっと早く読みたかった…!」と思ったデザイン本たち。
中には、デザインの先輩に教えてもらった本や、私自身が見ながら真似して練習した本もあります。
✔ 視覚的に学べる!
✔ 図解・マンガでわかりやすい
✔ Canvaやパワポですぐ使える!
そんな基準で厳選しました。
そして最後には、「まだ読んでないけど気になるおまけ本」も紹介しています。
ぜひ、自分に合いそうな1冊を見つけてみてくださいね。
デザイン初心者が本を選ぶときの3つの視点
「おすすめ本」って検索すると、ズラーッとリストが出てきますよね。
でも、正直どれもよさそうで迷いませんか?私はめちゃくちゃ迷いました(笑)
しかも初心者の頃って、自分に何が足りないのかも分からないんです。
だからこそ、「この3つの視点」で選ぶのがおすすめです。
①目的別に選ぶ:見た目改善?言葉?仕事の資料?
まずはここ。
「あなたは何のためにデザインを学びたいのか?」を考えてみてください。
たとえば、
- SNS投稿やバナーを整えたい → 配置や余白の基礎が学べる本
- 資料やチラシの見栄えを良くしたい → 実務で使えるデザイン本
- 商品やサービスをもっと伝えたい → コピーや言葉の設計が学べる本
…というように、目的が明確になると、“今の自分に合った一冊”が自然と見えてきます。
②図解・マンガで学べるかどうか
初心者にとって、これは超重要!
私も昔、活字ばかりのデザイン書を買って、3ページでそっと閉じました(あるある…)。
難しい用語や理論が並ぶと、読むのがしんどいんですよね。
逆に、図解やマンガが豊富な本は、視覚で理解できるからスーッと入ってくる。
「なるほどデザイン」や「けっきょく、よはく。」は、その代表格です。
イラストが多い=子どもっぽい、という印象を持つ人もいるかもしれませんが、
むしろプロの世界でも「ビジュアルで理解する力」が重視されてる時代です。
③読んで終わりにしない
“実践型”かどうか
最後にチェックしてほしいのが、「読むだけで終わらない構成になってるか」。
これ、意外と見落としがちなんですけど、
“真似できる作例”や“Before→After”が載っている本は、確実に力がつきます。
「本を見ながらCanvaを触ってみる」
「レイアウトの写経をしてみる」
「1枚チラシを実際に作ってみる」
こういう使い方ができる本は、読んだあとすぐ実務で活かせるし、身につき方が段違いです。
【必読】初心者が読むべきデザイン本3選+気になるおまけ1冊
本屋に行くとデザイン書が山のようにあって、正直「どれが自分に合うの?」って迷いますよね。
ここでは、私自身が「これ、最初に読んでよかった!」と心から思えた3冊と、
まだ読めていないけど“めちゃくちゃ気になっている1冊”を、おまけでご紹介します。
すべて初心者目線で、すぐに実務に役立てられる本ばかりです。
①『なるほどデザイン』
配置と構成の“理由”がわかる
📘 筒井美希 著
これは、大先輩に教えてもらった本でもあり、私が最初に「視覚的に学べて感動した本」です。
タイトル通り、“なんとなく”やっていた配置や色使いが「なるほど!」に変わります。
- 文字の強弱のつけ方
- 情報の整理の仕方
- 読み手の「目線の動き」まで考えた構成
すべてがイラストや事例でわかりやすく解説されていて、
「見る→真似る→分かる→できる」のサイクルが自然に回せる構成なんです。
Canvaで資料を作っている人や、SNSデザインで「なんか違う…」と感じている人にこそ読んでほしい。
まさに、“デザインの基礎”を学べる一冊です。
📌 この本の魅力をチェックしたい方はこちら!↓
②『けっきょく、よはく。』
見た目が激変!“余白”で整える
📘 ingectar-e 著(漫画でわかるバージョン)
実はこの本、私は最初、漫画じゃないバージョンを買って読みました。
でも正直…「けっきょくよはくって、けっきょくなんなんだーーー!」って、頭を抱えてたんです(笑)
そんなとき、漫画になって再登場したこの本を読んで、ようやく理解できたんです。
- 「余白がなぜ大事なのか」
- 「どこに、どれくらい空ければいいのか」
- 「ごちゃっとした見た目がどう変わるのか」
それが、視覚的に・テンポよく・かみ砕いて解説されていて、スーッと入ってくる。
私もこの本をきっかけに、Instagram投稿やバナーの余白の取り方が劇的に変わりました。
デザインが「整ってるね」って言われるようになったのは、この本のおかげです。
📌 この本の魅力をチェックしたい方はこちら!↓
③『会社のデザイン業務
困ったさんに贈る本』
実務向け「伝わる」資料術
📘 むかいさやか 著
この本は、私のデザインの師匠である むかいさやかさんが書いた本です。
ただの「やさしいデザイン本」じゃありません。
この本には、デザインの基礎だけでなく、「伝えるための考え方」がぎゅっと詰まっているんです。
私は当時、自分のデザインにどこか自信が持てずにいました。
でも、さやかさんの考え方に触れて、考えながらデザインするようになってから──
「見た目」だけじゃなく「想いが伝わる」デザインが作れるようになったんです。
今では、人にデザインを教えるようになり、プロとしてご依頼を受ける機会も増えました。
その軸になっているのが、まさにこの本に書かれている内容です。
✔ 社内のPOPやチラシを任された人
✔ パワポ資料を「見やすくしたい」と悩む人
✔ デザインがわからず一人で悩んでいる人
──そんな方にこそ、手に取ってもらいたい一冊です。
📌 この本の魅力をチェックしたい方はこちら!↓
④【気になる本】
『セールスコピー大全』
“言葉の力”もデザインの一部?
📘 阿部広太郎 著
これは、まだ読んでいないけどずっと気になっている1冊。
最近つくづく思うんです。
デザインって「見た目」だけじゃなくて、「言葉の設計」ができて初めて完成するって。
- SNSのキャッチコピー
- LPの見出し
- チラシやPOPの一言
どれも「デザインの一部」として超大事。
この本では、そんな“売れる言葉の作り方”が具体例と一緒に学べるみたいなんです。
今読んでいる3冊で“見た目”を整えられるようになったら、
次はこの本で“言葉”の力を鍛えたい。そんな「次のステップ」に入れたい1冊です。
📌 この本の魅力をチェックしたい方はこちら!↓
読んで終わりにしない!
学んだ知識の活かし方
本を読んで「なるほど〜」と思ったのに、数日後にはすっかり忘れてた…
そんなこと、ありませんか?(私はあります…何度も…)
デザインの本って、読みやすいし、感動ポイントも多いんですけど、
読んだだけじゃ“使える”ようにならないんですよね。
だからこそ、「どうやって実践に落とし込むか」が超重要!
ここでは、私が実際にやってみて効果があった方法を3つご紹介します。
①Canva・PowerPoint・Instagramで“すぐ試す”
本を読んだら、まずは手を動かすのが一番!
- CanvaでSNSバナーを作ってみる
- PowerPointで資料を1ページリデザインしてみる
- Instagramで「余白」を意識した投稿をしてみる
どんなに小さなことでも、読んだ直後の“やってみる熱”が冷めないうちに行動することがカギです。
私も『けっきょく、よはく。』を読んだあと、即Canvaを開いて余白を調整してみたんですが、
それだけで「お、デザイン変わった?」って言われたんです。小さな変化でも、気づかれると嬉しいですよね。
②「言葉→配置→色→余白」の順で
スキルを育てる
いきなり「全部整ったデザインを作ろう!」とするのは…正直、しんどいです。
私も最初、それで挫折しかけました。
だから、順番を決めて、段階的に学ぶのがおすすめ。
- 言葉(伝わるキャッチコピーや見出し)
- 配置(どこに、なにを置くか)
- 色(トンマナ、テーマカラーの選び方)
- 余白(どこを空けて、何を引き立てるか)
この順番で練習していくと、一つずつ「気をつける視点」が増えて、ぐんと成長できます。
特に初心者のうちは、一気にやろうとせず“1テーマに集中して練習する”方が習得が早いと感じました。
「今日はキャッチコピーに集中」「次は色選びを意識してみよう」──そんなふうに、分けて取り組むだけでグッとラクになります。
③写真に撮ってCanvaで再現!
“勝手に改善プロジェクト”をやってみる
これはちょっとマニアックかもしれませんが、私がやって本当に力がついた方法です。
- 本に出てくるデザイン例を写真に撮って、Canvaに貼り付ける
- その上から、同じデザインをトレース(再現)してみる
- できたら、自分なりに「ちょっと変えてみる」とさらに◎
この「勝手に改善プロジェクト」は、“見て終わり”を防ぐための小さな練習場です。
SNSでよく見るバナーやチラシなども、
「私ならこうするかも」「あ、この配置見やすい」と観察していくと、日常が教材になります。
地味だけど、本当に効きます(笑)
よくある質問:初心者がデザインを学ぶ上での壁と解決法
「デザインを学びたいけど、こんな悩みが…」
そんな声をたくさん聞いてきましたし、私自身もまったく同じことを思っていた時期があります。
ここでは、初心者がよくつまずく3つの壁と、その乗り越え方をお伝えします。
①「センスがないから無理…」
と思ってしまう
これ、本当によく聞きます。
でも、最初にハッキリお伝えしておきたいのは──センスは不要です。
デザインに必要なのは、“整える力”や“読み手への配慮”。
そしてその多くは、学ぶこと・繰り返すことで誰でも身につくスキルです。
私も最初は「色合いが変…」「レイアウトがごちゃごちゃ…」と、何度も凹みました。
でも、紹介した本を読みながら少しずつ試していく中で、
「なぜ変なのか」「どうすれば見やすくなるのか」が自然とわかってくるようになったんです。
②無料の情報では学びきれない?
YouTubeやSNSにも、デザインの情報はたくさんありますよね。
私もいろいろ見まくりました。でも、こう思ったんです。
「部分的なテクニックは分かるけど、全体像が見えない…」
たとえば、
・Canvaでの操作方法は分かるけど、そもそもどこに何を置けばいいのか?
・色の選び方は紹介されてるけど、どんな順番で考えればいいのか?
──そういう“つながり”が見えないままだと、断片的な知識で終わってしまうことが多いんですよね。
その点、本は「体系的に」「順序だてて」学べるという強みがあります。
「初心者向けにちゃんと順序が設計されてる」から、迷わず安心して読み進められるんです。
③続けられない/飽きてしまう
これは、私もかなり悩みました…(3日坊主の常習犯です)
でも、あるとき気づいたんです。
「練習が退屈」なんじゃなくて、「成果が見えない」から飽きちゃうんだって。
だから私は、成果が目に見えるようにちょっと工夫しました。
- Before→Afterを並べて保存しておく
- SNSで画像プレゼント企画をやってみる
- 本に書いてあったことを“自分の投稿で試す”日を決めてみる
たとえば、Canvaでバナーを作って「●●に使える画像、欲しい方いますか?」と呼びかけてみると、
反応をもらえることもありますし、自然と「誰かのために作る」練習にもなります。
少しずつでも、「前より整った」「なんか良くなった」って実感できると、
続けるモチベーションが全然違ってきます。
「できない」って感じたときこそ、学びの伸びしろが一番あるとき。
大丈夫。ゆっくりでも、着実に前に進めば、
気づいたときには「あれ?私、けっこうデザインできてるかも」って思える日がきます。
【初心者向け】
次に読むべき応用書や勉強方法
今回ご紹介した本で、基本的なデザインの考え方や“整える視点”が身についてきたら、
次はステップアップのタイミングです!
「もっとデザインを深めたい」
「応用的なこともできるようになりたい」
そんな方のために、“次に読むべきおすすめジャンル”と、“他の学び方”をご紹介します。
①配色やタイポグラフィの専門書を読んでみる
最初の3冊は「全体のバランス」や「構成」にフォーカスした本が多かったですが、
次におすすめなのは、配色や文字まわり(タイポグラフィ)に特化した本。
ここを強化すると、作品の「洗練度」が一気にアップします。
📘 たとえばこんな本もおすすめ:
- 『配色アイデア手帖』:テーマ別に色の組み合わせが学べる
- 『ほんとに、フォント。』:フォントの選び方と使い方が実例でわかる
色や文字は、ちょっと変えるだけで印象がガラッと変わるから、学んでおいて損はありません。
📌 この本の魅力をチェックしたい方はこちら!↓
②実践ワークブックで手を動かす
「読むだけじゃなく、やって覚えたい!」という方には、
ワークブック形式の本や課題付きの教材がおすすめです。
中でも「バナー制作」や「名刺リデザイン」「フライヤー模写」など、
“実際に手を動かす前提で書かれた本”は、成長スピードがぐんと上がります。
📘『デザイン入門教室[特別講義]実践編』などは、
レイアウトを作りながら「なぜそうするのか?」が学べて、思考力も鍛えられます。
📌 この本の魅力をチェックしたい方はこちら!↓
③Udemy・YouTube・有料講座で学びの幅を広げる
独学に限界を感じてきたら、動画教材やオンライン講座を取り入れるのもおすすめ。
- Udemy → 実務特化の講座が豊富(IllustratorやCanva実践など)
- YouTube → 短く学べるが、体系的な理解には向かない
- 有料講座 → フィードバックがもらえるものを選ぶと効果大
ちなみに、私も最初はYouTubeばかり見ていたけど迷子になって、結局本に戻ったタイプです(笑)
だからこそ、「本で土台を作ってから動画へ」の順番をおすすめします。
学び方に“正解”はありませんが、目的やライフスタイルに合った方法を選ぶことが続けるコツです。
あなたにとって心地よいペースで、次の一歩を踏み出していきましょう!
結論:デザインはセンスより
“考え方”と“順番”で学べる
「デザインって、感覚的で難しそう…」
そう思っていた私も、1冊の本との出会いから、少しずつ世界が変わり始めました。
今回ご紹介したのは、
“センス”ではなく、“伝えるための仕組み”を学べる本ばかりです。
- 配置のルールを知る
- 余白の効果を理解する
- 言葉の力を意識する
この順番で学ぶだけでも、驚くほどデザインは伝わりやすくなります。
しかも、どれも初心者向けにやさしく書かれていて、読みやすいものばかり。
もし、今「自分のデザインに自信がない」と感じているなら、
まずは “気になる1冊”から読みはじめてみてください。
読んで、真似して、ちょっとずつ手を動かしていくと、
「前より整ってる!」「なんか伝わりやすくなった!」という変化がきっと出てきます。
その変化が、次の行動につながり、
やがて「仕事としても頼まれるデザイン」に進化していくこともあります。
📌ちなみに、デザインだけでなく、“導線そのものを整える考え方”にも興味がある方は、
私が配布している無料動画講座とチェックリストも活用してみてください。
『売り込まずに売れるWeb導線講座&チェックリスト』はこちら↓
あなたの「届けたい」という気持ちが、
ちゃんと“伝わる”デザインにつながりますように。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
運営者についてはこちら↓
Story
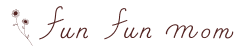
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b226083.9c5ca5e8.4b226084.ec5cde6a/?me_id=1213310&item_id=17521544&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5174%2F9784844365174.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b226083.9c5ca5e8.4b226084.ec5cde6a/?me_id=1213310&item_id=21082006&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4450%2F9784802614450_1_4.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b23a900.61dde0e7.4b23a901.209128e7/?me_id=1285657&item_id=12964818&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F01125%2Fbk4295020486.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b226083.9c5ca5e8.4b226084.ec5cde6a/?me_id=1213310&item_id=20204980&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2617%2F9784827212617.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b226083.9c5ca5e8.4b226084.ec5cde6a/?me_id=1213310&item_id=20983184&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9046%2F9784815619046_1_7.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b226083.9c5ca5e8.4b226084.ec5cde6a/?me_id=1213310&item_id=19480860&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2081%2F9784802612081.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b226083.9c5ca5e8.4b226084.ec5cde6a/?me_id=1213310&item_id=21201702&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4309%2F9784815624309_1_3.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)